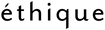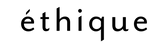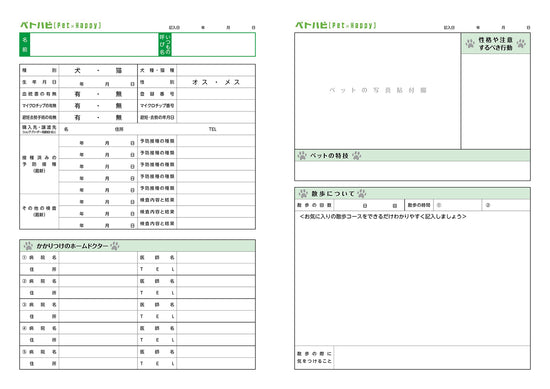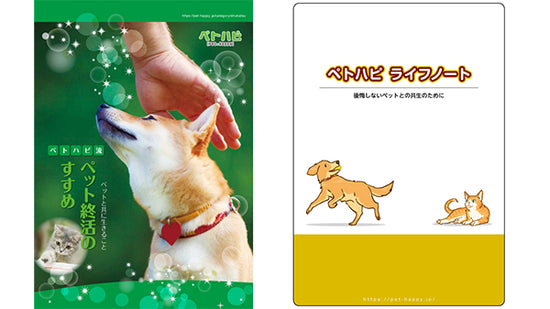ペットにも理想的な最期を。
「終活」という言葉は「終わりのための活動」の略語です。私たち人間の場合は、人生の最期を自分の理想的なものとし、後悔のないようにするための事前準備のことをいいます。
「縁起でもない」と考えることを遠ざけてきた人生の最期。今では、背を向けることなく受け止める大切さを感じ、さまざまな準備を始める「終活」が広がっています。
こうした変化は、人間が飼うペットたちにも大きな影響を与えています。住環境の変化や獣医療の進歩、ペットフードの改良などにより寿命が延び、飼い主とともに生きる時間が長くなりました。そして、ペットに対する飼い主の考え方も「家族の一員」へと変化してきました。
癒し癒され、幸せいっぱいのペットとの生活。しかしながら、ペットは人間の4倍の速さで年を重ねていきます。そこには「別れ」という避けられない現実があります。人間よりも短い生涯であるからこそ、飼い主が「ペットの終活」をきちんと考え、できるだけ後悔のない、理想的な最期を迎えたいものです。
ペットの終活のすすめ
-

第7回 「供養スタイル」を検討する
愛するペットが“最期の時”を迎えたら、あなたはどうしますか? いつかは別れが来るとわかっていても、実際にその日を迎えると、どうしたらよいのかと困惑してしまいます。大切な家族の一員であるはずなのに、どのように供養すべきか迷ってしまうのです。
自宅で写真を飾り、大好きなおもちゃやおやつをお供えする。ペット専用の共同墓地に埋葬する。ペットのお墓を購入して埋葬する。ペットの供養の仕方に「形」はありませんので、どれもがよい供養と言えるでしょう。
大切なことは、ペットを思い出し、いつまでも忘れないでいてあげることです。納得のいく供養ができるように、ペットが元気なうちから検討しておくことをオススメします。
ペット終活コラム
-

ペットロス症候群にならないために“いま”やるべきこと
ペットロスとは、その文字のとおり「ペットを失うこと」を意味します。犬や猫などのペットを失うと、さまざまな症状が精神的、身体的、あるいは双方に起こる場合があります。それを「ペットロス症候群」といいます。
ペットとのお別れで後悔しないためにいまからできること。ペットとお別れした後も、素敵な思い出だけを残したい。そのためには、日ごろから「愛犬・愛猫に対してできることは、すべて、いますぐにやる」という覚悟と行動が必要です。そしてその姿勢こそが、やがて自分をペットロス症候群から救うことに繋がるのです。
ここでオススメする「ペットの終活」は、そのネーミングからシニア期を迎えた犬や猫を対象にしていると思われがちなのですが、実際には愛犬・愛猫の年齢に関わらず、いますぐに始めていただきたいものなのです。
-

【レポート】なぎさグループとペットメディ"ペトハピ"が「ペットの終活」セミナーを開催
霊園・墓石の総合企業・なぎさグループの新社屋・市川ゲートウェイにて、「ペットの終活」セミナーが開催されました。
このセミナーは、なぎさグループ友の会「やすらぎ21」の会員さんを対象としたものです。
「やすらぎ21」は、もしものときに残された家族の負担を軽減することを目的とした終身会員システムです。入会金(1万円)のみで年会費や積立金がかからないにも関わらず、葬儀費用などの会員割引といったさまざまなサービスやイベントに参加できるなど、魅力的な会員組織です。ペットの終活セミナーもその一環として開催されました。
今回はその「ペットの終活」セミナーの模様をお送りします。